渓流釣りにおける初心者と上級者の違いとは何なのか。初心者が釣れていないときでも、上級者は間違いなく釣果を得ている。今回は、仕掛け・エサの使い分けなど、より上を目指すための応用編をみていこう。
(アイキャッチ画像提供:TSURINEWSライター荻野祐樹)

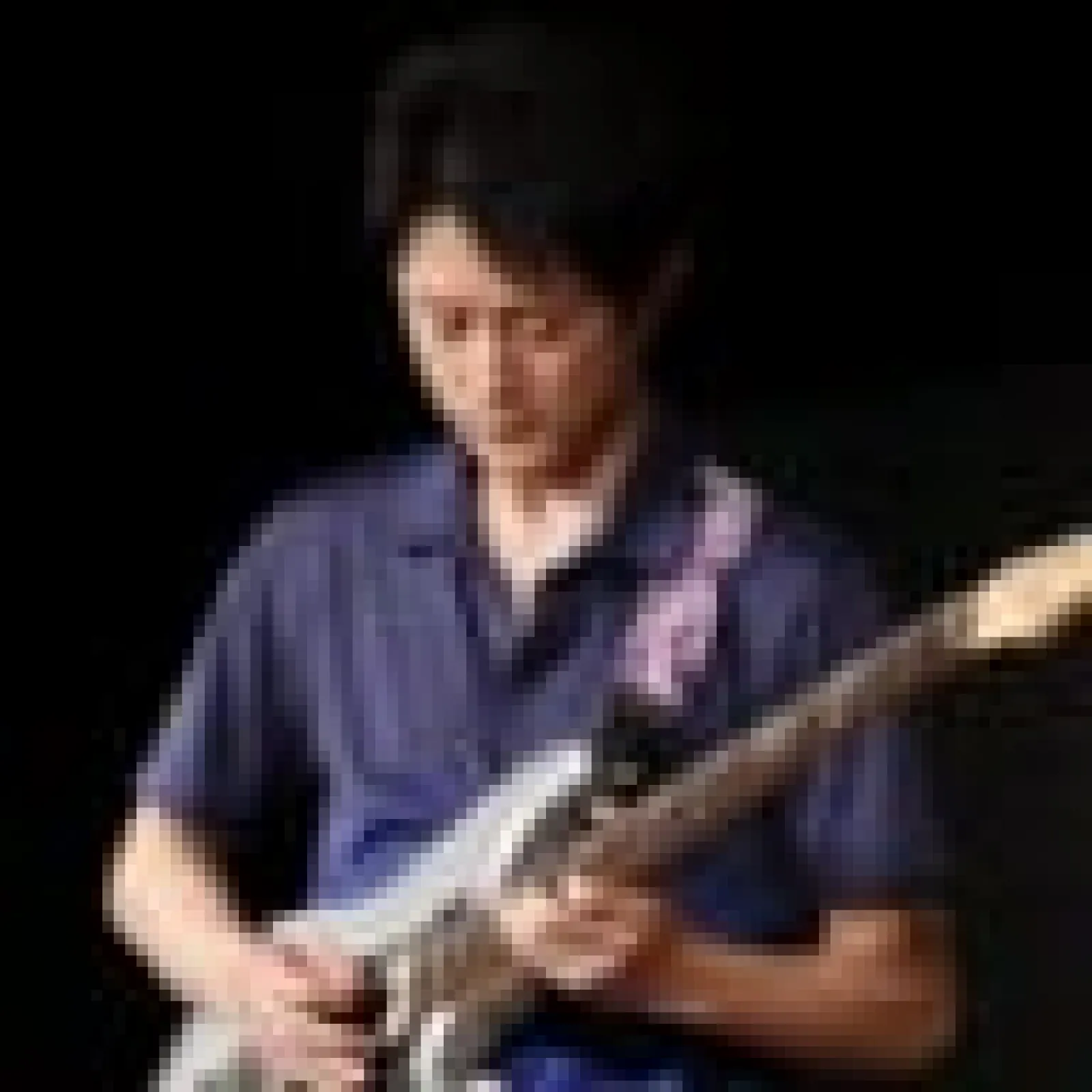
初心者と上級者の違い
一番の違いは、思考に現れる。上級者の思考は非常に柔軟だ。渓流釣り初心者の場合、釣れる前は何らかの形で得た情報に固執してしまう傾向にある。実際始めたばかりの頃の著者がそうで、管理釣り場でよく釣れていたイクラに絶大な信頼をおいており、どんな時もイクラばかり使っていた。
また、固定概念も強く持っており、「絶対この場所にいるはずだ」と信じて何度も仕掛けを流し、広範囲を攻めていなかった時期もある。季節や水温など、刻一刻と変化していく状況に柔軟に対応する力を養うことこそ、渓流釣りが上達する一番の秘訣と言える。
さらには、事前にしっかり睡眠時間を確保したり、適度に食事をして集中力を確保しておくことも重要だ。
ベテラン釣り師は仕掛けを自作する
著者も含め、ベテラン渓流師はほぼ必ず仕掛けを自作している。その理由を解説しよう。
自分の釣り方が確立している
ベテランは、ポイント選びや釣り方など、渓魚に対してどのようにアプローチするかが確立している。また、使用するラインの銘柄や目印、針も全て決まっていることが多いが、それにはその人なりの理由が必ずあるのだ。
コスパが良い
市販仕掛けは1つ当たりが高価。細糸ゆえに、ちょっとしたトラブルで仕掛けがダメになりやすい渓流仕掛けは、市販品を買うよりも、自作した方が圧倒的にコスパが良い。
状況変化に強い
ベテランの場合は、通っている川の状況を詳しく把握している。そのポイントごとに竿や仕掛けの長さを予め調整して用意することで、トラブルなく釣ることができる。時に河川ライブカメラの映像などを確認し、川の状況に合わせて仕掛けを作ることも多い。
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
筆者の仕掛け紹介
では、著者が実際に使用している通し仕掛けを画像で紹介しよう。
 渓流釣り仕掛け(作図:TSURINEWSライター荻野祐樹)
渓流釣り仕掛け(作図:TSURINEWSライター荻野祐樹)上の図のように、著者の通し仕掛けは実にシンプルなので、チチワの結び方や針の結び方を覚えて慣れてしまえば、すぐに作れるようになる。自作仕掛けで渓魚に出会えるとなお嬉しいもの。是非仕掛け作りをマスターしよう。
状況によってエサを使い分けよう
より釣果を伸ばそうと思えば、時期や川の状態によってエサを使い分けることが重要となる。これはルアー用語でいう「マッチ・ザ・ベイト」だ。
解禁直後はイクラ
雪解け水により低水温となる解禁直後は、流石の渓魚達も活性が非常に低い。だが、イクラの臭いが渓魚達を狂わせると言われている。栄養価が高い上に臭いが強いエサなので、解禁直後はイクラが無双状態になることが多いのだ。
スレ始めたらすぐに川虫
上記の理由で、解禁直後にあちこちの河川でイクラが使用されると、渓魚達はあっという間にスレてしまう。こうなってくると、日頃から食べ慣れている川虫が最も警戒されにくいのでオススメだ。
川虫は渓魚がいる場所の少し下流に行けば、割とどこでも採集できる。3~4月はキンパクをメインエサとし、食い渋りにヒラタを使用する。
 キンパクは川虫の中でも最高のエサ(提供:TSURINEWSライター荻野祐樹)
キンパクは川虫の中でも最高のエサ(提供:TSURINEWSライター荻野祐樹)濁りの入った本流ではクロカワムシもよく釣れるし、6月以降はコオロギのようなサイズになるオニチョロも面白いエサだ。ただし、川虫が羽化する4月と6月以降は入手が難しくなるので、その際はミミズやブドウムシなど別のエサを用意しておこう。
 クロカワムシは濁りのある本流で有効なエサ(提供:TSURINEWSライター荻野祐樹)
クロカワムシは濁りのある本流で有効なエサ(提供:TSURINEWSライター荻野祐樹)ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
自分で捕獲したミミズ
ミミズは釣具屋でも購入できるが、山や畑の土を掘って採集するドバミミズは大変活きが良く、動きも激しい上に、臭いも非常に強い。これは雨後に絶大な効果を発揮するので、是非試してみてほしい。
乾期・夏場はブドウムシや現地調達の昆虫
落下昆虫を意識し始める5月頃~初夏以降の曇り時、水量が減る時期は、白く目立つブドウムシが強い。その他、夏場は現地で採れる小型のバッタやセミもエサになる。
難易度が高い場所を攻めてみよう
ある程度釣り方が分かってきたなら、初心者がスルーしがちな場所も積極的に攻めてみよう。こういった場所は、その難易度故に場荒れしていないので、予想外の釣果が望める。
木の真下
そのまま仕掛けを投入すると間違いなく仕掛けが引っかかってしまうので、竿抜けポイントになりやすい。こういった場所では4m程度の短い竿・軽いオモリを使用し、水の抵抗を仕掛けで受けさせるようにしつつ、竿を倒して送り込んでいく。極端に短い仕掛けを使用する「チョウチン釣り」で狙ってみるのも面白い。
 木の真下は工夫して狙おう(提供:TSURINEWSライター荻野祐樹)
木の真下は工夫して狙おう(提供:TSURINEWSライター荻野祐樹)水深が極端に深い場所
滝壺のような極端に深い場所は、流れが非常に複雑になる上、すぐに流されてしまうので難易度が非常に高い。2B~6Bのような思いオモリを使用して、一気に底まで沈めて良型を狙ってみよう。ただし、上手く流さないとすぐに根掛かりしてしまうので注意しよう。
チャラ瀬
あまりの浅さゆえに、「どうせこんな場所にはいないだろう」……と侮るなかれ。渓魚は、自分の体が隠れる程度の水深があれば、初夏以降は普通に出てくる可能性がある。水深が20cmもあればヒットする可能性があるので、軽いオモリで竿を立て気味にし、水面付近を意識して流してみよう。根掛かりしても簡単に外しに行けるので、怖がらずに攻めてみてほしい。
テクニックを磨いて釣果を伸ばそう
今回紹介したことを意識し始めてから、著者の釣果は目に見えてアップした。最初の1匹さえゲットしてしまえばなんとなく要領が掴めて来るので、より釣果を伸ばせるよう、色々と工夫してみてほしい。趣向を凝らしてゲットする1匹は非常に価値があり、得も言われぬ感動を味わえるはずだ。
<荻野祐樹/TSURINEWSライター>
The post 渓流エサ釣りステップアップ解説 【仕掛け自作・エサ使い分け・竿抜けポイント狙い方】 first appeared on TSURINEWS.ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT












